それぞれの出題範囲からの問題数と傾向を考える。
まとめると、
【権利関係】 14問・・・・28% (2割)
【法令上の制限】10問・・・・20% (2割)
【宅建業法】 21問・・・・42% (5割)
【税その他】 5問・・・・10% (1割)
これからの勉強方法は、宅建業5割、権利関係と法令上の制限を各2割、税その他1割の割合にしよう。
あとのこり3か月ちょっと、、、です。
<<出題範囲と問題数について>>
土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
<3.法令上の制限・税・その他STEP28>
たとえば、土砂災害の危険性が高い土地、耐震性を持っている建築物の構造などが出題されます。
出題の配分は、
土地について1問
建物について1問
土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること
<2.権利関係 上巻・下巻>
いわゆる「権利関係」といわれる分野で、出題数は(7)の次に多い14問です。
不動産の所有権・抵当権などの権利や、不動産の売買・賃貸借などの契約による権利の変動が出題されます。
出題される法令は、
民法(10問)
借地借家法(2問)
区分所有法(1問)
不動産登記法(1問)
土地及び建物についての法令上の制限に関すること
<3.法令上の制限・税・その他 STEP2~19>
いわゆる「法令上の制限」といわれる分野で、出題数は(7)と(2)の次に多い8問です。
無造作な土地開発や建物建築などを制約するための様々な規制(土地の利用制限、建物の建築制限など)が出題されます。
土地の利用制限「土地開発をするときは○○の許可が必要である」
建物の建築制限「△△地区では工場を建築できない」
出題される主な法令は、
都市計画法(2問)
建築基準法(2問)
国土利用計画法(1問)
宅地造成等規制法(1問)
土地区画整理法(1問)
農地法(1問)
宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
<3.法令上の制限・税・その他 STEP20~23>
不動産にまつわる税金について出題されます。
過去に出題例のある税金は、
不動産取得税
登録免許税
固定資産税
印紙税
贈与税
相続税などです。
出題数が上記から2問
宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
<3.法令上の制限・税・その他 STEP25~27>
不動産の公正な取引を促進する制度や、不動産に関する統計などが出題されます。
不動産に関する統計は最新のものが出題されるので、間違えて過去の統計を学習しないように注意しましょう。
出題される主な法令・実務は、
住宅金融支援機構(1問)
景表法(1問)
不動産に関する最新の統計(1問)
宅地及び建物の価格の評定に関すること
<3.法令上の制限・税・その他 STEP24>
不動産の価格を決めるための基準を定めた法令などが出題されます。
地価公示法または不動産鑑定評価基準からの出題が多くみられます。
これら2つを学習しておけば十分でしょう。
地価公示法
不動産鑑定評価基準
宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること
<1.宅建業法>
宅地建物取引業法は「宅建業法」と省略されて呼ばれることも多いですね。
出題数20問
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」から1問
++++まとめ++++++
[法令上の制限] 10問
土地・建物(2問)
都市計画法(2問)
建築基準法(2問)
国土利用計画法(1問)
宅地造成等規制法(1問)
土地区画整理法(1問)
農地法(1問)
[権利関係]14問
民法(10問)
借地借家法(2問)
区分所有法(1問)
不動産登記法(1問)
[宅建業法]21問
出題数20問
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」から1問
[税・その他]5問
地価公示法
不動産鑑定評価基準
住宅金融支援機構(1問)
景表法(1問)
不動産に関する最新の統計(1問)
不動産取得税
登録免許税
固定資産税
印紙税
贈与税
相続税などです。
出題数が上記から(2問)
【権利関係】14問・・・・28% (2問)
【法令上の制限】10問・・20% (2問)
【宅建業法】21問・・・・42% (5問)
【税その他】 5問・・・・10% (1問)
にほんブログ村
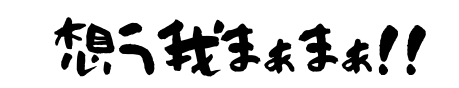
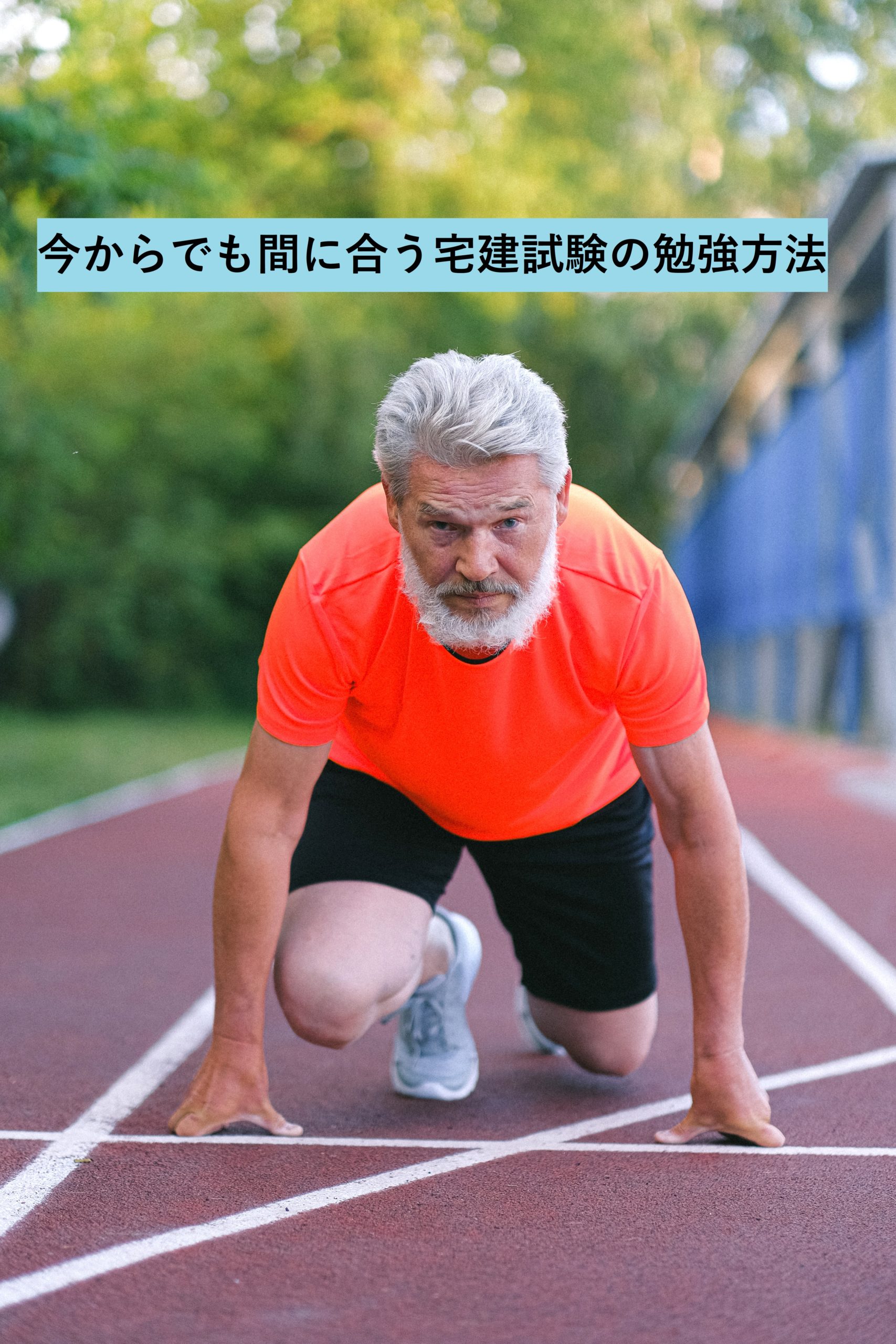


コメント